新年でワンシーズン。そのくらい俳句にとっては重要な季節。
新年に限定的に使われる動物や植物があるんですね。日本人のお正月・新年に対するスペシャル感や愛着がなせる業でしょうか。
まずは初心者でも取り入れやすい四季折々の季語を、「いちばんわかりやすい俳句歳時記」からご紹介していきます。
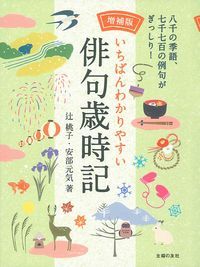
俳句初心者にお勧め本
発売日: 2016年10月13日頃
著者/編集: 辻桃子・安部元気
出版社: 主婦の友社
発行形態: 単行本
ページ数: 528p
ISBNコード: 9784074184323
俳句初心者でも文字を見ただけで思い浮かびやすい季語に絞っています。玄人っぽい季語って使うのに躊躇します。技術に自信がないとその季語を使う勇気がわかないといいますか。
新年の季語:動物
初鶏・初雀・初鳩・初鴉(はつがらす)
初声といって、これらを含むさまざまな鳥の鳴き声を指すもののあります。鳥類と初が組み合わさると新年になるようです。初鶏は元旦をイメージさせ、初鴉は最初の日暮れをイメージします。鳩とスズメはちょっと謎です。
新年の季語:植物
橙・楪(ゆずりは)・福寿草・若菜(七草粥の七草)・千両・万両・葉牡丹
正月飾りや鏡もちに使われる植物が多いですね。そんな中で葉牡丹が入るところが初心者には謎です。
俳句初心者にお勧め本

- 柏餅 かしわもち
- 粽とともに、五月五日の端午の節句菓子として知られる。新粉生地で餡を包み柏の葉でくるみ、蒸した菓子。柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないため、子孫繁栄の意味がある。

